70年前の小説『ペスト』に再び注目が集まる

#ペスト #トリアージ
#感染症 #池田大作全集
新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、感染症の広がる社会を舞台にしたフランスの作家、カミュのおよそ70年前の小説『ペスト』に再び注目が集まり、日本国内の文庫版はこの2か月で15万部余りが増刷されて、累計発行部数が100万部を突破しました。
『ペスト』はフランスのノーベル文学賞作家、アルベール・カミュが1947年に発表した長編小説で、ペストの感染が広がって外部と遮断された社会の中で感染症という見えない敵と闘う市民の姿を描いています。
官僚たちの初期反応は2020年と同じ
この作品はアルジェリアの要港で起きる物語だ。平凡な街に変化が訪れるのは、ある医師が死んだ鼠に気づくところからはじまる。そして、その鼠の死骸は街のいたるところで発見され、異常なほどに膨れ上がっていく。行政は、幾百もの死骸を焼却するが、その終わりがない。
そのうち、医師のもとには、おかしな症状を見せる患者が急増していく。高熱で頸部のリンパ腺が腫脹し、脇腹に斑点ができ、もがき苦しむ患者たちだ。そして、彼らは、次々と死亡していく。ペストが街を蝕もうとしていた。
“
<天災というものは、事実、ざらにあることであるが、しかし、そいつがこっちの頭上に降りかかってきたときは、容易に天災とは信じられない。この世には、戦争と同じくらいの数のペストがあった。しかも、ペストや戦争がやってきたとき、人々はいつも同じくらい無用意な状態にあった>
カミュの描く官僚たちの、初期段階での反応が興味深い。
“
<「いかにも、市民が不安になっていることは事実だ」と(中略)「それに、おしゃべりってやつが万事大袈裟にしちまうんでね。知事はこういわれたよ――『まあ、早いとこすますとしましょうや。ただし目立たないようにね』って。もっとも、知事は結局空騒ぎだと確信しておられるんだがね」>
『ペスト』でも描かれていた、錯乱した患者が街に飛び出すシーン
この小説には医療崩壊に至るさまも書かれているが、そこはあえて省略し、私は人間の心理的な記述に注目したい。小説では、舞台の街が閉鎖される。家族や愛する者たちとの別離。文通もできない状態。その環境は行政に向くことになる。
“
<彼らの最初の反応は、たとえば、施政当局に罪を着せることであった>。
そして、日々のようにペストによる死者数が発表されるようになったが、
“
<市中で誰一人、ふだんのときには毎週何名ぐらいの人が死んでいるものなのか、知っているものはなかった>。
さらに、事態の深刻さに人々が気づいたあとのエピソードも興味深い。
“
<あるカフェが「純良な酒は黴菌を殺す」というビラを掲げたので、アルコールは伝染病を予防するという、そうでなくても公衆にとって自然な考え方が、一般の意見のなかで強まってきた>。
“
<また別のところでは、ハッカのドロップが薬屋から姿を消してしまったが、それは多くの人々が、不測の感染を予防するために、それをしゃぶるようになったからである>。
これは2020年の出来事だろうか。
また、このような記述があるのには、驚かざるを得ない。
“
<ある朝一人の男がペストの兆候を示し、そして病の錯乱状態のなかで戸外へとび出し、いきなり出会った一人の女にとびかかり、おれはペストにかかったとわめきながらその女を抱きしめた>。
これは2020年の出来事だろうか。
また、現在では、新型コロナウィルスのPCR検査による。偽陰性(陰性ではないのに陰性とされること)や偽陽性(陽性ではないのに陽性とされること)の問題がある。検査を抑えたい医療関係者。しかし、検査をしてほしい、という一般人。この小説にも、医療従事者と一般人が見解で対立するシーンがある。一般人が街を抜け出し恋人に会いたいと懇願する箇所だ。
“
<「証明書をひとつ書いていただけないかどうか(中略)、僕が問題の病気にかかっていないことを確認するという意味での証明書なんですがね。」(中略)「僕はその証明書を書いてあげることはできません。(中略)あなたが僕の診療室を出た瞬間から県庁に入る瞬間までの間に病毒に感染することがないとは、僕には保証できないからです(中略)。この町にはあなたのようなケースのものが何千人といるんですよ。しかしその人たちを出してやるわけにはいかないんです」>
人間はずっと変わっていないのかもしれない
ペストについて、なすすべもなくなった人びと。そこで宗教家が、信者にむかって説教をするのだが、このくだりも大変に人間の変わらぬ何かを見せてくれるようだ。
“
<「今日、ペストがあなたがたにかかわりをもつようになったとすれば、それはすなわち反省すべき時が来たのであります。心正しき者はそれを恐れることはありえません。(中略)あなたがたは今や罪の何ものたるかを知るのであります。(中略)皆さんを苦しめているこの災禍そのものが、皆さんを高め、道を示してくれるのであります」>
“
<「われわれは神を憎むか、あるいは愛するか、選ばねばならぬからである。そして、何びとが、神を憎むことをあえて選びうるであろうか?」>
東日本大震災と新型コロナウィルスを比較する向きもあるが、カミュの想像力は恐ろしいほどで、登場人物にこう語らせている。
“
<「まったく、こいつが地震だったらね! がっと揺れ来りゃ、もう話は済んじまう……。死んだ者と生き残った者を勘定して、それで勝負はついちまうんでさ。ところが、この病気の畜生のやり口ときたら、そいつにかかわっていない者でも、胸のなかにそいつをかかえているんだからね」>
カミュは、現代を見つめていたようだ。いや、それは正しくなく、人間というものがずっと変わっていないと教えてくれているのかもしれない。
ペストは終わった。新型コロナはどうなるか?
さきに引用した宗教家がどうなるか。これは実際の小説を読んでもらいたい。私も、多くの方がそうであるように、新型コロナウィルスの影響がいつ軽微になるのか、不安をいだいている。けっきょく、情報番組が語ることは、どこでもいっしょで、手洗いとうがいと、人混みを避けることしかない。インフルエンザも、新型コロナウィルスも、罹患するという意味では被害者だが、知らぬ間に自分が加害者になりうる可能性を有している。それがさらに不安を加速させていくのだ。できるだけのことをやっていくしかない。
“
<引っきりなしに自分で警戒していなければ、ちょっとうっかりした瞬間に、ほかのものの顔に息を吹きかけて、病毒をくっつけちまうようなことになる。自然なものというのは、病菌なのだ。そのほかのもの――健康とか無傷とか、なんなら清浄といってもいいが、そういうものは意志の結果で、しかもその意志は決してゆるめてはならないのだ。>
たゆまぬ市民の注意と、そして、代えがたい犠牲の重なりの中で、ゆっくりと、ゆっくりと、終結の音が聞こえてくる。死亡者は減っていき、安堵の雰囲気が広がる。市民は、鼠が元気に走り回るさまを見つける。しかし、急激に安穏とした空気が広がるわけもなく、不安もじれったいほどの速度でしか払拭されていかない。
そしてついに、街はペスト終結の宣言をおこなう。
“
<暗い港から、公式の祝賀の最初の花火が上がった。全市は、長いかすかな歓呼をもってそれに答えた>
この小説は現代に通じる人間心理を書く。災害に襲われながら、それが通り過ぎるとなんら教訓を引き出そうとしない「懲りない」人間たちを、突き放すでもなく、諦観するでもなく、ただただ冷静に記述していく。その冷静さが不気味なほどに読むものを恐怖させる。終結をただただ祝うものたちは、それまでの犠牲をすべて忘れている。死んでいった男女を思い返すこともない。しかし、それが皮肉なことに人間の強みであり、罪のなさであり、人間性なのだ。
さらにこの小説は、単なるハッピーエンドにもしない。街中が歓喜に包まれるかというと、そう単純なものとしても描かれない。終結を祝うものはいる。いっぽうで、大切な人間を失ったもの、なによりも、平和を喪失した人びとの欠落感とともに描かれる。
そして、小説はこのように終わる。
“
<おそらくはいつか、人間に不幸と教訓をもたらすために、ペストが再びその鼠どもを呼びさまし、どこかの幸福な都市に彼らを死なせに差し向ける日が来るであろうことを>
私たちは新型コロナウィルスが静まったあと、なんらかの教訓を引き出すだろうか
(幻冬舎plusの記事より引用)
2005.3.11 スピーチ(2004.9〜)(池田大作全集第97巻)より
13 ″無理だと言うより、まずやってみよう″
二十世紀を代表するフランスの作家に、ノーベル文学賞を受賞したアルベール・カミュがいる。
先日、カミュの世界的な名作である『ペスト』の日本語訳の初版本を、創価学園の「学園優秀会」の代表が届けてくださった。学園出身の大学生等で、良き兄として、後輩の栄光寮生の育成に尽力してきたメンバーである。
『ペスト』は、私も青春時代に愛読した懐かしい一書だ。
カミュは、鋭い言論でナチスと戦ったレジスタンスの闘士である。その彼が、第二次世界大戦が終結して間もない一九四七年に発表したのが、この小説であった。題名に掲げられた「ペスト」は、急性伝染性の病気である。死亡率が高く、史上、数々の大惨事をもたらしてきた。しかし作者カミュは、この「ペスト」をたんなる疫病としてだけでなく、人間を虐げ、蝕み、滅ぼしていく「不正や悪」の象徴としてつづったのである。
物語では、ペストに見舞われた都市で、犠牲者が広がっていく様相と、その惨事に立ち向かって勇敢に戦う人々の姿が描かれている。
若き英才の諸君に心から感謝し、この名作を通して語っておきたい。(以下、届けられた創元社刊の『ペスト』〈宮崎嶺雄訳〉から引用・参照)
小説の舞台は、北アフリカのアルジェリアの都市オラン。
ある日、悪疫ペストの発生を示す兆候が現れた。やがて少しずつ、犠牲者が出始める。しかし、本来なら、いち早く正確な情報を集め、都市を挙げて対策を行うべき責任を持つ人々が、なかなか徹底的な対策を講じようとしなかった。そのようすを、物語では鋭く、綿密に描いている。
この都市の医師組合の幹事は、″自分には対策を講ずる資格がない。権力もない″と、即座に手を打たなかった。県知事もまた、″社会に騒ぎを起こしたくない。総督府にも命令を仰がないといけない″と、迅速な行動を怠った。新聞は、事態を軽く見て、真実を広く知らせようとしなかった。
多くの人々は、自分は大丈夫だろうと行動を起こさなかった。また、皆、不安を感じながらも、真実から逃げようとした――。
カミュは、「みんな自分のことを考えていた」と描写している。その「自己保身」と「無責任」と「無関心」の蔓延が、悪疫ペストの拡大を許してしまったのだ。
小説の中で、ある人物が「決して明日に延ばすな」との格言を語る場面がある。
悪は絶対に放置してはならない。電光石火で手を打つことが、皆を守ることになる。
ぺストの拡大によって、ついに都市は外部から遮断される。患者の増大に、当局の対応は追いつかなくなった。
そのとき、タルーという青年が、医師のリウーとともに、有志で保健隊を結成。悪疫ペストとの戦いを開始した。それは、人々の心に巣食う″あきらめ″との戦いでもあった。
保健隊の結成について「そんなことはなんの役にも立ちませんよ。ぺストなんて、とても手に負えるしろものじゃないですからね」と言う人に、青年タルーは毅然と答える。
「それはわからないでしょうね、あらゆることをやってみた上でないと」
あきらめることは簡単である。むしろ、何も行動しない人間が、いちばん、早くあきらめる。
しかし真の勇者は、最後まで執念をもって戦い、行動するものだ。″あらゆることをやってみる″ものだ。
14 同苦と誠実で困難と闘う
ぺストの蔓延。それは、いつ終わるともしれない、死と悲惨の極限の状況であった。
そのなかを懸命に戦い続けた中心者の医師リウーについて、小説では、こうつづられている。
「公明な心の掟に従って、彼は断乎として犠牲者の側に与し、人々や市民たちと一緒になって、彼等が共通にもっている唯一の確実なもの、即ち愛と苦痛と追放とを味おうとした。
従って、市民たちの苦悶の一つとして、彼が共にしなかったものはなく、いかなる情況も、同時に彼自身の情況でなかったものはないのである」
仏法の「同苦」の精神にも通じる行動といえよう。
また、青年タルーは、「心の平和に到達するためにとるべき道」について聞かれ、それは「共感ということだ」と語っている。彼らは、″自分さえよければいい″という利己主義を振り捨てた。
人の苦しみに同苦し、人のために行動する。その「共感」と「連帯」に生きるなかにこそ、自分自身の「心の平和」もあることを知っていたのである。わが学会の尊き同志の姿をほうふつさせる。
さらにまた、リウーは訴えた。
「ペストと闘う唯一の方法は、誠実さということです」「僕の場合には、つまり自分の職務を果すことだと心得ています」
真の誠実とは、人々のために、なし得る限りのことをなすことである。みずからの使命に生ききることだ。
物語には、若い新聞記者も登場する。
この青年は、当初、ぺストに侵された都市から脱出し、愛する人に再会するという、わが身の幸福ばかりを考えていた。しかし、医師リウーたちの献身の姿に心打たれ、同志に加わる。そして、ようやく得た脱出のチャンスもなげうって、行動を続けた。
青年は言った。
「自分一人が幸福になるということは、恥ずべきことかも知れないんです」
この青年の心の革命が、物語の重要なテーマの一つでもある。
-
前の記事
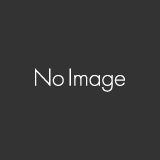
オンライン学習 2020.05.05
-
次の記事

マスクやトイレットペーパーの不足 2020.05.05