悲しみの戦隊ヒーロー

今日(3月2日)は、「中国残留日本人孤児の日」です
1981(昭和56)年3月2日、厚生省の招待で中国残留日本人孤児47名が、肉親探しの為に、初めて公式に来日、36年ぶりに祖国の土を踏みました。
僕が中国残留孤児について調べるきっかけとなったのが 1986年に放送された
スーパー戦隊シリーズの『超新星フラッシュマン』です
なぜこの問題と戦隊ヒーローが関係あるんだと思われるでしょうが、
恐竜戦隊ジュウレンジャー →ジュラシックパークによる恐竜ブーム
救急戦隊ゴーゴーファイブ→ 阪神大震災で活躍したレスキュー隊
魔法戦隊マジレンジャー →ハリーポッター
天装戦隊ゴセイジャー →遊戯王などのカードゲーム
海賊戦隊ゴーカイジャー →ワンピースやパイレーツオブカリビアン
というように戦隊ヒーローは当時の時代背景をモチーフにすることが多いです
スーパー戦隊シリーズで初めて2号ロボが登場したのがフラッシュマンですが、
フラッシュマンの5人は赤ちゃんのときに、エイリアンにさらわれ、宇宙に連れて行かれてしまいます。そこでフラッシュ星人に助けられ、フラッシュ星で育てられることになります。
そして20年が経ち、地球に“改造実験帝国メス”の魔の手が伸びてきた時に、故郷を救うため「フラッシュマン」が地球に帰ってくるというストーリーです
彼らは親の顔を知りません。
敵との戦いの結末とは別に、彼ら5人の親探しが視聴者の興味を引きつけられました。
この“親探し”というテーマは、中国残留孤児という当時の社会問題から発送されました
中国残留孤児とは、第2次大戦後、諸事情で帰国できず中国に残された日本人孤児のことです。戦後、未帰還の孤児は1万4,000人以上と言われていましたが、中国との国交がなかったこともあり、調査が開始されるまで終戦から36年もの歳月を要しました。
日中国交回復によって日本に生みの親を探しに来ても、幼少期に生き別れた方はまず日本語すら分かりません。
友人・知人もいません。
社会制度その他もろもろが異なります。
親の方も「あの混乱の中で既に死んでいる」と思い込んでいる場合もありました。
こういった様々な要因があって、日本の環境にも馴染めず孤立するケースが頻出。日本語が話せず仕事に就けないなどの窮状を支援するため、現在はさまざまな支援団体が発足し、支援を続けています。
小説「新・人間革命」19巻 宝塔の章より
36 宝塔(36)
沖縄、広島、長崎と進められた青年部の反戦出版は、一九七九年(昭和五十四年)には一都一道二府二十四県に広がり、五十六巻を数えた。
さらに、八一年(同五十六年)からは、「戦争を知らない世代へII」として、再び出版を開始。
八五年(同六〇年)までには、新たに二十四巻が発刊され、全四十七都道府県を網羅するに至った。
この十二年間にわたる青年の地道な取り組みによって、全八十巻、三千二百人を超える人びとの平和への叫びをつづった″反戦万葉集″が完結したのである。
各県の青年部は、郷土と戦争の関係を考えながら、「空襲体験」「出征兵士の体験」「戦時下の生活」「外地からの引き揚げ体験」など、テーマを絞り込んでいった。
出征した兵士たちの証言からは、戦地での壮絶な行軍や悲惨な食糧事情、また、上官の横暴、戦友の凄惨な死などが語られていった。
そのなかで加害者としての側面も浮かび上がっていった。
宮城県や和歌山県、岡山県などの青年たちは、加害者としての視点から反戦出版を進めた。
和歌山県の青年部は『中国大陸の日本兵』を上梓した。日本兵は中国で何をしたかを記した証言集である。
″日中友好を考えるならば、たとえ目を背けたい歴史であっても、真摯に凝視しなければならない″と、青年たちは考えたのである。
証言は、永久に自らの胸の内に秘めておこうと決めてきた、兵士の″忌まわしい過去″である。
取材に応じてくれた一人の元兵士は、取材を契機に、やめていた酒を飲み始め、夜ごと、苦悶の叫びをあげるようになった。彼の妻は、そのたびに馬乗りになって、彼を押さえつけなければならなかった。
その後、落ち着きを取り戻し、再取材できたが、青年たちは加害者のもつ、心の傷の深さをあらためて知った。加害者もまた、軍国主義の被害者であることを痛感したのである。
ゲーテは、近代の戦争というものの本質をこう指摘している。
「近代の戦争は、それがつづいている間は多くの人を不幸にし、済んでしまっても誰一人をも幸福にはしない」
37 宝塔(37)
熊本県の青年部も、加害者の側からの視点で反戦出版を行っている。
当初、メンバーは、熊本の第六師団は最強であったと聞かされてきたことに着目し、軍人であった人たちに、「なぜ第六師団は強かったか」との質問をぶつけてみた。
多くの人が快く取材に応じてくれ、戦争の武勇伝を語る人も多かった。
しかし、再度、取材に行き、戦闘で勝利したあとの捕虜の扱いなどを問い始めると、次々と取材を拒否された。
なかには、加害者としての体験を語ってくれた人もいたが、テープを起こして、確認してもらうために原稿を持っていくと、こう言うのだ。
「本にはしたくない。辞退させていただく」
また、虐殺の証言をしてくれた壮年がいた。事実関係のあいまいなところは、戦友に確認してくれることになった。
だが、翌日になると、「あれは俺の勘違いだった」の一点張りで、虐殺自体を否定するのだ。
戦友から証言することに反対されたようだ。
結局、五十人ほどに取材して、証言集に掲載することができたのは、十七人であり、そのうち九人は仮名での掲載が条件となった。
被害と加害の両面が明らかにされてこそ、戦争の全貌が浮かび上がる。それでこそ、真実の反戦出版となるのだ。
残忍な行為に加担した人も、会って話を聞いてみれば、皆、好々爺であった。「出征前は、鶏一羽殺すこともできなかった」という人もいた。
″なぜ、そんな人が無感覚に人を殺せるようになってしまったのか″
編集メンバーは、取材を続け、討議を重ねていくなかで、そこに、戦争というものの魔性の仕組みがあることに気づく。
「自分が死にたくないという本能を、逆に利用して人を殺させるのだ。
ひとたび戦場に押し出されたら、もはや、その流れに逆らうことはできないものだ」
そして、「戦争になってからでは遅い。その前に、戦争なんかさせないために、諸外国との友好の推進など、政治を、平和の方向に動かすことだ」というのが、青年たちの結論であった。
「青年は心して政治を監視せよ」とは、戸田城聖の叫びである。メンバーは、その言葉の重さをかみしめるのであった。
38 宝塔(38)
外地での抑留や引き揚げを反戦出版のテーマとした県もあった。
引き揚げ港となった博多港を擁する福岡県青年部でも、『死の淵からの出帆――中国・朝鮮引揚者の記録』を発刊している。
引き揚げの道もまた、悲惨であった。
そこに登場する、ある婦人は、満州(現在は中国東北部)の開拓民として入植。二人の子どもをもうけたが、二人とも病死した。
三人目の子どもの出産を間近に控えた一九四五年(昭和二十年)八月十三日、突然、避難命令が出された。夫は徴兵されていた。
彼女は家財道具を売り払い、義父、母と馬車に乗って、二百人ほどの開拓民らと共に逃げた。
盗賊団にも襲われた。ソ連軍の爆撃も受けた。機銃掃射の標的にもなった。恐怖のために精神が錯乱し、自分の子どもを次々と馬車から投げ捨てる母親も見た。
一カ月間、逃げ続け、ソ連軍の収容所に入った。女性は、次々と暴行された。彼女は頭を丸坊主にし、顔に墨を塗って難を逃れた。
彼女は、腸チフスにかかったが、女児を出産する。しかし、母乳も出なかった。
ゆでたコーリャンの上澄みを、必死になって飲ませた。だが、赤ん坊は日に日にやせ細り、四十四日目に死んだ。
彼女と母親は、三十人ほどの女性たちと収容所を脱出した。逃亡中、さらに発疹チフスにもかかった。騙されて売られそうにもなった。
自暴自棄になり、アヘンを飲んで自殺を図ったが、飲んだアヘンはすべて戻してしまった。舌を噛み切っても、死ぬことはできなかった。
盗賊団に襲われ、逃げ惑うなかで、苦楽を共にしてきた母親とも離れ離れになってしまった。
彼女が九死に一生を得て、帰国したのは一九四六年(昭和二十一年)十月であった。
戦争の最大の犠牲者は女性と子どもである。だからこそ、女性は、平和を守るために立ち上がらなければならない。社会の主役として、正義の声をあげるのだ。
「もし、非暴力が人類の守るべき教義であるならば、女性は未来の創造者としての地位を確実に専有するでありましょう」とは、マハトマ・ガンジーの確信である。
39 宝塔(39)
反戦出版では、子どもたちの被害に焦点を当てたものも少なくない。
そして、戦争がその国の″今″を破壊するだけでなく、″未来″をも破壊する非道な行為であることを、様々な角度から訴えている。
東京の青年部は、「学童疎開」した子どもたちを取材し、疎開先での空腹、いじめ、教師の横暴など、抑圧された生活を浮き彫りにした。
滋賀県の青年部は、戦時中の教育者を中心に取材を進めた。
そのなかには、″忠君愛国″を訴え、満蒙開拓青少年義勇軍などに教え子を送り出した教師たちの、拭い去ることのできない罪悪感がつづられた手記もあった。
また、静岡県青年部の『みんな かつことをしんじてた――子供達の見た聖戦(1)』には、次のような話が紹介されている。
寝かすと「ママー」と泣く、ドレスを着たママー人形を、ロープで縛って木につるし、国民学校の教師が猟銃で撃つ。そして、少年たちに木刀で叩かせたというのだ。
子どもたちは、あの戦争を「聖戦」と教えられてきた。
それを真っすぐに受け止め、国のために戦おうと、予科練などに志願した少年も多かった。
この本には、こんな話も収められている。
農学校に通っていたが、志願して予科練に入り、その訓練途中に終戦を迎えた少年がいた。
彼は、母校である農学校に戻った。
授業中、ある教師は冷淡に言い放った。
「志願して兵隊に行った馬鹿者がいる」
それを聞いていた、同じ予科練帰りの少年が、教壇に向かって走り出し、教師に殴りかかったのだ。
信頼してきた大人たちに裏切られた、悲憤であったにちがいない。
この軍国主義教育が行われていった時代のなかで、「教育は児童に幸福なる生活をなさしめるのを目的とする」として、教育改革を叫び続けてきたのが、牧口常三郎であり、創価教育学会であった。
それは、命がけの平和建設の作業でもあった。
「植物は栽培によってつくられ、人間は教育によってつくられる」とは、フランスの思想家・ルソーが、『エミール』に記した名言である。
40 宝塔(40)
反戦出版に携わった青年たちは、人びとの証言から、国家神道を精神的支柱とした軍国主義思想の恐ろしさを、痛感するのであった。
守るべき中心は国民ではなく国家とし、国のために勇んで死んでいける人間をつくることが教育であったのだ。それは万人を「仏」と見る、生命尊厳の仏法の法理とは対極の思想である。
経文には「国土乱れん時は先ず鬼神乱る鬼神乱るるが故に万民乱る」とある。鬼神とは、現代的には思想といえよう。
思想の乱れ、すなわち誤った思想が、国家を、社会を、民衆を狂わせ、やがて国をも滅ぼしてしまうことを戒めているのだ。
青年たちは、この反戦出版を通して、一人ひとりの胸中に生命尊厳の哲理を確立する広宣流布こそ、恒久平和への直道であることを深く自覚していった。
また、人間の生命を制御し、善の方向に変えていく人間革命なくして、平和の創造はないことを強く実感したのだ。
反戦出版全八十巻の完結は、平和への一大金字塔として大きな反響を広げ、多くの識者が「偉業に脱帽」「反戦平和への一大証言集」等と絶讃の声を寄せてくれた。
反戦出版が完結して間もなく、山本伸一は青年部の首脳と懇談した。
「よく頑張ったね。大変な壮挙だ。これで戦争体験の風化をくい止め、反戦平和の一つの砦を築くことができた」
すると、青年の一人がはつらつと応えた。
「先生は、世界平和のために一人立たれ、ベトナム戦争の即時停戦や日中国交正常化の提言等を、命がけで発表してくださいました。
″私たちも弟子として平和のために戦いを起こそう。先生に続こう″との思いで、この活動に取り組みました。
そう心を定めると勇気が出ました。力がわきました。この反戦出版は師弟共戦の賜物です」
「ありがとう。君たちが後に続いてくれると思うと力が出る。二十一世紀を『平和の世紀』『生命の世紀』にするために共に戦おうよ」
反戦出版の完結は、終わりではなく、始まりであった。それは伸一と青年たちの、新しき平和運動の旅立ちを告げる号砲となったのである。
-
前の記事

最後のセンター試験 2020.05.30
-
次の記事
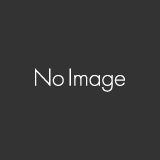
小説 新人間革命で学ぶ世界史(ギリシア編) 2021.04.13